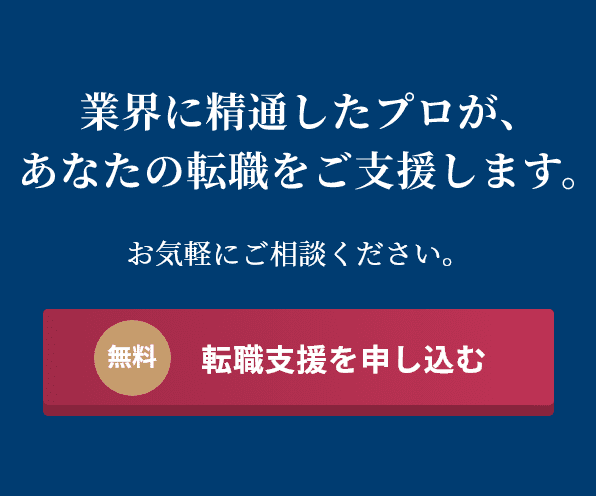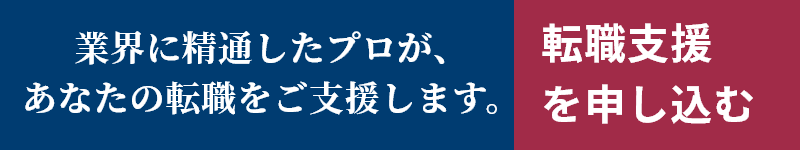企業インタビュー
一般社団法人日本能率協会 企業インタビュー|審査だけじゃない。“多角的な支援”でお客様の課題解決に貢献する”唯一無二の認証機関”
目次
1942年に設立され80年以上の歴史を誇る、一般社団法人日本能率協会。
食品安全に関わる各種審査規格においては、国内トップの認証件数を誇ります。
そんな日本能率協会で、現在、審査登録センターのセンター長、そして審査部の部長として、審査業務全般の責任を担う伊藤様ですが、実は求人に出会うまで“審査員”という職業の存在を知らなかったといいます。
今回は同会で活躍する伊藤様、前田様、横田様に入社のきっかけや仕事の魅力、そして職場の雰囲気についてお話を伺いました。

家族の一言が導いた、「審査員」という仕事との運命的な出会い
― まずは、これまでのご経歴についてお聞かせください。
伊藤様:大学卒業後、建設会社で約13年間勤務していました。
主に土木工事の現場に携わり、キャリアの後半には設計業務も担当するようになりました。現場のことも設計のことも理解している点が、私の強みだと感じています。その後、2001年に一般社団法人日本能率協会へ転職し、現在に至ります。
― 長年建設会社でご活躍されていたなかで、なぜ審査員に転職しようと思われたのですか。
伊藤様:当時、私は37歳だったのですが、建設会社での経験を活かして、何か新しいことにチャレンジできないかと、少しずつ転職活動を始めていました。そんなとき、偶然家族が新聞で日本能率協会が審査員を募集している記事を見つけて、「これ、あなたに向いてるんじゃない」と勧めてくれたんです。記事を読んでみると、「自分にもできるかもしれない」と思い、興味を持ちました。
前職の会社でもISO認証を取得しており、実際に審査員の方が審査に来る様子は見たことがありました。ただ、当時は自分がその仕事をするなんて、まったく想像もしていませんでした。そもそも審査員という職業を認識しておらず、募集記事を見て初めて「こういう仕事もあるんだ」と知りました。応募要件を見ると、自分でも応募できそうだと思い、思い切ってチャレンジしてみることにしました。
審査部の部長として、審査業務全般の責任を担う
― 現在はどのようなお仕事をされているのですか。
伊藤様:現在は、審査登録センターのセンター長、そして審査部の部長として、審査業務全般の責任を担っています。
具体的には、審査後に作成される審査報告書の内容確認をはじめ、審査員の教育の場となる技術会議の企画・運営、審査員の評価や最終的な審査結果の判定、お客様情報の変更管理など、多岐にわたる業務を担当しています。
入社当初は、審査計画を担当していました。
これは、お客様の希望日程と審査員の空き状況、審査員の専門性を照らし合わせながら、最適な審査計画を練り上げていく仕事です。約3年間この業務に携わり、さまざまな審査員やお客様がいらっしゃることを知りました。その経験が、現在の業務にも大いに活かされていると感じています。
― 何名ほどの審査員を管理されているのですか。
伊藤様:現在、マネジメントシステムの審査員が150〜160名、GAPという製品認証を担当する審査員が約35名おり、全体では200名近い審査員が在籍しています。
審査に関わる頻度はさまざまで、年に数回しか行かない人もいれば、100日以上審査に行かれる方もいらっしゃいます。審査員の特性を見極めながら、審査の質を維持できるようマネジメントしています。
― 審査業務においては、どのような使命感を持って取り組んでいらっしゃいますか。
伊藤様:審査において最も大切なのは、「公平であること」です。
お客様の仕事のやり方や、企業規模、上場・非上場といったものに関わらず、どの認証基準に対しても公平に判断することが、私たち審査員の責務です。実践するのは簡単ではありませんが、公平な審査ができなければ、認証機関としての信頼を保ち、継続していくことはできないと感じています。
そして、公平な審査をした先に、お客様の企業や従業員の方々、取引先、ひいては社会全体に良い循環を生み出していくことが、私たちの目指すところです。
その良い循環をつくるための最初の一歩を担っているのが私たち審査員です。だからこそ、「歯車がしっかりとかみ合い、好循環を生み出せるように」という使命感を持って日々取り組んでいます。
「経営者も気づけていない課題をあぶり出す」、それこそが最大のやりがい
― どのようなときにやりがいを感じられますか。

伊藤様:審査員としてやりがいを感じるのは、お客様ご自身がまだ気づいていない課題を明らかにできたときです。
もちろん、経営者の皆さまはマネジメントレビューや内部監査などを通じて、社内の課題はある程度把握されていると思います。ただ、それでも見落とされている点や、どう対処すべきか悩んでいることがあるケースも少なくありません。
事前にそうした課題感を共有いただいていれば、審査を通じて少しでもその答えを導き出せるよう努めています。実際に明確な結果が得られることはそう多くはありませんが、「審査で得られた情報を命題と合わせて、こういうことが課題につながっているのではないでしょうか」とお伝えすることはできるので、非常にやりがいがあります。
審査が終わると、多くのお客様が安堵の表情を浮かべて「ありがとう」と声をかけてくださいます。その瞬間、「お客様のところに来て本当によかったな」と感じます。
― これまで多くの審査を経験されてきた中で、印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
伊藤様:一番印象に残っているのは、お客様に「もう二度と来るな」と言われたことです。
その方は50代後半ぐらいの方だったのですが、当時私は40歳前後で分別のない若造に見られていたのだと思います。指摘すべき点を丁寧にお伝えし、内容そのものにはご納得いただけたのですが、顔を潰されたと受け取られてしまったようです。
もう一つ印象的な事例は専門性の高い企業で、会社としては「国家資格の一般的な資格を持っていれば、力量要件としては問題ない」という認識を持たれていました。しかし、管理部門の方々は、力量要件の見直しが必要だと感じていたようです。
審査を行い当該部門の責任者の方には「このままでは当部門に必要な専門的な力量が不足しているのではないでしょうか」と、お伝えしました。最終的には専門的力量が会社に必要だということに気づいていただき、改善していただけたので、結果としてよかったのではないかと感じています。
また、商品開発は企業にとって非常に難しいテーマで、良い製品を作ったとしても途中で頓挫してしまうケースもあります。
特に問題となるのが、「この製品をいつまでに開発し、リリースするのか」という最終的な意思決定権が曖昧なまま進んでしまうことです。本来であれば、営業責任者や企画・設計の責任者、経営層が責任をもって開発の進捗を見極め、「これはまだ完成とは言えないから中止しよう」といった判断を下す必要があります。しかしある企業では、製造現場で完全にはうまくいかなかったものが当初の発売期限に併せて市場に出てしまい、大きなクレームにつながってしまったことがありました。
この問題に関して審査で見てほしいと依頼を受け、一連のプロセスを確認して「最終的な意思決定を下す人が明確になっていますか」という話をさせていただきました。審査では結論は出ず継続的な課題となりましたが、少しは解決の糸口を示せたのではないかと思います。こうした瞬間に、「この仕事をやっていてよかったな」と感じます。
“一人前の審査員”になるまでに歩むステップ
― 審査員のキャリアプランについて教えてください。
伊藤様:職員の方も契約審査員の方も、基本的に歩むステップは同じです。
まずは、審査員評価登録機関である日本要員認証協会(JRCA)へ「審査員補」という資格の登録が必要になります。「審査員補」を取得するには、研修機関で研修を受ける必要があります。例えば、JRCAが認定している研修機関の品質マネジメントシステムの場合は、5日間の研修コースを受講し、合格するとJRCAに審査員補として登録できる仕組みになっています。
つまり、「研修を受ける → 合格する → JRCAに登録する 」という一連の流れを経たうえで、日本能率協会にご登録いただき、初めて審査員としてのトレーニングがスタートする形になります。
その後、「審査員補」から「審査員」へと昇格するには、テストのために審査へ行っていただき、所定の回数をこなし「十分に審査ができる」と当会が判断すれば、JRCAに審査員への昇格登録をしていただきます。審査員として資格登録ができれば、そこから本格的に審査員としてのキャリアがスタートします。契約審査員の場合は、審査業務に応じて報酬をお支払いする形になります。職員の場合は給与制となるため、報酬という扱いではありませんが、お客様から報酬がいただける審査員になれるということです。
審査員として実際に活動を始めるまでの期間は、人によって異なります。早い方であれば、1年ほどで現場に出られるようになりますが、中には1〜2ヶ月に1回しか稼働できないという方もいらっしゃいます。特に内部の職員の場合、なかなか外部の審査に出られないケースもあり、進み方には個人差があります。
1〜3年のうちには、リーダーを目指して研修を受けていただきます。2日間の研修を経て、リーダーウィットネスと呼ばれる審査を現地で3回受けていただき、すべてで「良好」という評価を得られれば、いよいよリーダーとしての活動が認められます。ここでようやく“一人前の審査員”として、スタートラインに立てます。当会でウィットネスに3回合格していれば、JRCAへの「主任審査員」の登録も可能になります。国家資格ではありませんが、主任審査員という公的な資格を取得することができます。
このように資格取得のステップは同じなのですが、JMA職員の方には審査計画や審査報告書の確認、最終的な審査結果の判定、営業なども行っていただくため、審査に携わる頻度はそれぞれ異なります。内部の業務をしっかり担ってほしいと考えている方には、月に1回程度のペースで審査に行ってもらえればと考えています。外に出て活躍してほしい方には、積極的に審査の現場に出ていただきます。
現在は特に、社内の業務もしっかり行いながら、審査活動にも並行して取り組んでいただける方を求めています。
― 審査研修コースは5日間あり、最終日に筆記があると伺ったのですが、合格率はどのくらいなのでしょうか。
伊藤様:はっきりとした数字までは分かりませんが、不合格になる方も一定数いらっしゃいます。研修期間中にしっかりと勉強しないと、合格するのは難しいと思います。
“経営革新の推進機関”として、審査業務にとどまらず多角的な支援ができるのが強み
― 他社にはない特徴や強みを教えてください。
伊藤様:私たちは「経営革新の推進機関」です。認証ビジネスを始めたのは1994年ですが、1942年から経営革新の推進機関としてスタートを切っています。「経営革新」とは何か、当時の理事長が紐解いた言葉を引用すると、「環境の変化や自発的な意志によって、製品・サービス、組織・システム、風土、活動の方法などを新たな発想で改革し、品質・生産性・個人の能力・働きがいを飛躍的に向上させること」とされています。
特に、近年非常に重要視されている「働きがい」も含めて経営革新であるというのは、非常に良い定義ではないかと思います。そういったことを私たちも標榜しており、お客様にも訴えていけるのではないかと思っています。幅広いマネジメントシステムを、この経営革新という言葉で提供していける、そこが非常に強い団体ではないかなと思っています。
例えば、他の認証機関の中には、電機業界や鉄鋼業界、建設業界、化学業界など、特定の業界が主体となり、業界の必要性に応じて設立された機関もあります。それに対して、私たちは特定の業界に属さない公平性が強みの一つです。さらに、製造業からサービス業まで、どのような視座でも対応できる点も強みです。
また、審査登録センターは一事業部門であり、日本能率協会には他にも展示会部門や教育研修部門といった部門もあります。必要に応じて一緒に活用していただくことや、審査と並行して研修を受けていただいたり、審査後に展示会にご参加いただいたりと、相互にメリットのある形でサービスをご提供できる体制が整っています。
単なる認証業務にとどまらず、多角的な支援が可能である点は、自信を持ってお勧めできる理由の一つです。

― 課題の解決にあたって、認証サービス以外のアプローチも可能ということでしょうか。
伊藤様:例えば、営業力を活かして「どこに売り込もうか」といった際には、展示会をご活用いただくこともできます。また、審査の中で何かしらの課題に気づかれた場合には、研修のご案内やサポートも行えます。こうした点は、当会ならではの強みだと思います。
前田様:私たちは審査機関としての役割を担っていますが、審査とそれ以外の研修は、明確に区別する必要があります。その点をふまえてお話しさせていただきますと、日本能率協会は「企業の総合病院」だと私は思っています。
お客様が抱えていらっしゃる課題はさまざまですが、日本能率協会には、そうした課題を全部署で解決へと導ける体制とコンテンツが整っています。
これは、他の組織にはない強みだと感じています。仮に日本能率協会で解決が難しいケースでも、日本能率協会コンサルティングのようなグループ会社もあるため、必ずどこかで課題を解決できる体制が整っています。「必ずお客様の課題を解決し、より良い方向へ導く」という強いプライドと責任感を持って、日々業務に取り組んでいます。
認証機関らしくない?自由な職場
― 働く環境について教えてください。
伊藤様:まず一つ特徴的なのは、フリーアドレス制を採用しており、好きな場所に座って仕事ができるようになっています。
役員室は一応ありますが、それ以外のスペースはすべてフラットなテーブルで構成されていて、誰とでも気軽に会話ができるオープンな環境です。以前は、3階と4階のフロアが日本能率協会のオフィスになっており、両フロアを自由に行き来できるようになっていました。しかし、「一緒に働く仲間は近くにいた方が良いのではないか」ということで、現在の形になりました。
また、2023年からは服装もビジネスカジュアルが基本となりました。ほぼ普段着に近いスタイルでも問題なく、かなり自由度が高くなっています。ただし、お客様との打ち合わせや外部訪問時には、TPOをわきまえた服装が求められます。
― お堅いイメージがあったのですが、自由度が高いんですね。
伊藤様:認証機関というと、どうしても堅いイメージを持たれがちですが、実際には意外と敷居が低いんです。フロアの改装も何度か行っているのですが、そのたびに「自由な発想が生まれるような空間をつくろう」と、上層部もさまざまな工夫を凝らしてくれているように感じます。
軽く体を伸ばせるような器具も置いてありますし、今年からは「芸術的な雰囲気の中で研修を行えば、より効果が高まるのではないか」という考えで、研修室に絵画も飾るようになりました。まだ具体的な効果はわかりませんが、ご来訪いただいた方からは「雰囲気が明るくなったね」といった声をいただいており、良い印象を持っていただけているのではないかと感じています。
もう一つ、特徴的なのが「さん付け」文化です。近年「さん付け」を導入する企業も増えてきていますが、当会はコンサルティング集団としてスタートした組織ということもあり、お互いの知識を尊敬しあい、先輩・後輩関係なく役職ではなく「さん付け」で呼び合う文化が根付いています。これは非常に良い文化だと思います。
― 御社で働く魅力はどこにあると思われますか。
伊藤様:審査登録事業に特化してお話しすると、私たちの仕事は「形あるモノ」を売る仕事ではありません。現場でのお客様との対話を通じて課題を見つけ出し、それを報告するという、形がないものを売りながら相手を幸せにする難しい仕事です。
その中で、私たちが最も大切にしているのは、審査登録サービスを通じて、お客様に「お願いしてよかった」と感じていただくことです。そのために、決して努力を惜しんではいけないと思っています。こうした想いに共感し、一緒に取り組んでくださる方であれば、きっとこの仕事の面白さややりがいを感じていただけるはずです。ご興味のある方は、ぜひご応募ください。
求めているのは”審査のプロ”
― どのような人材を求めていますか。
伊藤様:私たちが求めているのは、「審査のプロ」です。
「審査のプロ」としてまず求められるのは、公平・公正な視点で審査を行えることです。そのためには、誠実であることは欠かせません。次に大切なのが「傾聴力」です。相手の話をしっかり聞く力は、審査において非常に重要です。ただし、単に話を聞くだけではなく、湧き出る探求心がなければ審査員にはなれません。
さらに、集めた情報を的確に判断する「判断力」も必要です。
そして、最終的に審査結果をまとめて報告するうえでは、お客様にどのように伝えて、ご理解いただくかが重要になります。そういう意味では、「人間力」も必要です。つまり、「誠実さ」「傾聴力」「探究心」「判断力」「人間力」をバランスよく備えている方こそ、私たちが求める人材です。なお、2025年からは、ホームページ上でも「求める審査員像」を明確にお伝えしています。
― 御会ではどのようなバックグラウンドの方がご活躍されていますか。
伊藤様:当会では、特定の業界にこだわらず幅広く採用を行っており、これまでに入職された方々も多様なバックグラウンドをお持ちです。
例えば、鉄鋼メーカーの出身者や品質保証の責任者、電機メーカーや印刷業界、建設業界、金属加工業、食品関連の会社など、比較的製造業出身の方が多い傾向にあります。
ただし、製造業出身でなければ審査員になれないというわけではありません。むしろ、業界に染まっていない、これから審査という仕事を一から学んでいこうという姿勢のある方のほうが、この仕事には向いているのではないかと思います。すでに”自分の型”を持っている方よりも、当会で初めて審査業務に触れるようなまっさらな状態の方の方が、柔軟に業務を吸収していけるのではないかと思います。
― 審査員として活躍している方に、何か共通点はありますか。
伊藤様:「人の話をしっかり聞けること」が、大事だと思います。
お客様のお話をきちんと聞いて理解し、そこからさらに探究心をもって様々なことを聞ける方が、やはり活躍しているように感じます。審査の場では、つい間が持たなくなって、次々と質問したくなることがあります。
しかし、本来は一問一答ではなく、1つ質問をして10聞くようなイメージでないといけないと思います。それができることが、審査員として最も重要ではないでしょうか。私たち審査員が質問して判断するというよりも、お客様自身に「この規格に適合するために、こういった取り組みをしています」と説明していただき、それを聞くのが本来の仕事です。お客様から自然に話を引き出す能力こそが、審査員には必要だと思います。

前田様: 審査における商品は”審査員”であり、審査員の資質こそが最大のポイントになります。私たちは審査員の採用にあたって非常に厳しい基準を設けており、その中でも特に重視しているのが「人の話をしっかり聞ける人」であることです。
伊藤さんも先ほどおっしゃっていましたが、「傾聴力」が非常に重要です。これまでの経験に自信がある方ほど、つい自分の話をしたくなる傾向がありますが、私たちが採用するのは“人の話をきちんと聞ける人”です。実際に「良い審査員」と言われる方々は、皆さん共通して“聞き上手”です。
なぜ“聞き上手”な方を求めているかというと、聞き上手な方は基本的に人から好かれるんです。審査では経営者だけでなく、現場で働く方々にもたくさんお話を伺います。ただ、現場の方は、審査員が来ると緊張してしまうことが多いんです。そうした中で、いかに本音で話をしていただいき、改善点を見出していくかが、非常に大事な作業になるわけです。そうした点に長けている方を、私たちは積極的に採用しています。
そして、伊藤さんもお話しされたように、一緒に学びながらブラッシュアップしていけるところは、日本能率協会審査登録センターの大きな特長だと思っています。
認証件数No.1。その先に目指すのは…
― 今後の展望を教えてください。
伊藤様:おかげさまで、FSSCやFSMS、JFSなど、食品安全に関わる各種審査規格において、当会は日本国内の認証機関の中で認証件数No.1となっています。最終的には認証件数だけでなく、「審査内容も含めて信頼性No.1」と言われる存在を目指していますが、信頼度を客観的に測る明確な尺度がまだないため、現時点では認証件数を一つの指標として掲げています。
私たちが目指しているのは、「JMA(日本能率協会)に頼んで本当によかった」「JMAじゃないとダメなんだ」とお客様から言っていただけるような、信頼される認証機関になることです。そうした声を直接いただけることが、私たちにとって何よりの喜びですし、それこそが最高の評価だと思っています。
部門を問わず“やりがい”をもって働ける職場
― 最後に、応募を検討されている方へメッセージをお願いします。
伊藤様:審査員は、非常にやりがいのある仕事だと感じています。
経営者の方に直接質問し、お話を伺える機会は、他にはなかなかありません。審査そのものだけでなく、審査業務をバックヤードから支える仕事も含めて、社会に貢献できる仕事です。少しでも興味がある方には、ぜひチャレンジしていただきたいと思っています。
私たちは時に、お客様から「先生」と呼ばれることがあります。しかし、私たちはコンサルタントでも、モノを教える仕事でもなく、それは間違いです。むしろ、常に謙虚な姿勢で学び続けることが求められます。常に変化し続ける規格に対応するために、学習意欲は欠かせません。審査員の中には80歳を超える方もいらっしゃいますが、皆さん現役で学び続けていらっしゃいます。
日々学び続け、審査の場では審査に集中し、役割を全うすることが何より重要です。学習意欲を持ち、立ち位置を変えて企業に貢献したいという方のご応募を、心よりお待ちしています。

横田様:転職してもうすぐ1年になりますが、まず驚いたのは、職員一人ひとりがやりがいを持って前向きに仕事に取り組んでいることです。審査部門に限らず他の事業部やバックオフィス部門も、与えられた業務をこなすだけでなく、自ら仕事を見つけ、課題を見出して取り組んでいる職員が多い印象があります。
会社全体として「チャレンジする姿勢」を大切にしており、職員一人ひとりがその想いを持って取り組んでいるように思います。”働いている職員”こそが、JMAの魅力の一つだと思います。
私は人事を担当しておりルーティンワークも多いのですが、それだけでなく社外とのやりとりや事業部門の方々と対話する機会も多くあります。また、事業もスピード感があり、風通しも良いので、堅い職場をイメージされていると、ミスマッチになってしまうかもしれません。
審査部門に限らずやりがいのある職場で、私自身「転職してよかった」と感じています。ぜひ、私たちと一緒に働きましょう。皆さまのご応募を心よりお待ちしています。
会社概要
- 会社名
- 一般社団法人 日本能率協会
- 会社概要
- 1.マネジメントに関する調査及び研究
2.マネジメントに関する情報の収集及び提供
3.マネジメントに関する人材の育成及び指導
4.マネジメントの高度化に寄与する表彰、資格認定及び普及啓発活動
5.マネジメント及びマネジメントに関連する技術及び産業振興に関する会議、展示会等の開催
6.規格適合に拠るマネジメントシステム及び製品、サービスに係わる第三者認証及び登録業務サービスの提供
7.地球温暖化防止にかかわる各種検証及び環境マネジメント支援業務サービスの提供
8.マネジメントに関する内外関係機関等との交流及び協力
9.その他本会の目的を達成するために必要な事業 - 会社設立日
- 1942年(昭和17年) 3月30日
- 代表者名
- 山口 範雄
- 所在地
- 東京都港区芝公園3―1―22 日本能率協会ビル
- 従業員数
- 142
企業新着求人(最新5件まで表示)
-
- 求人番号:150845
海外展開あり
大手企業
土日祝休み
業界最大手の社団法人
サステナビリティ 事業開発・審査
- 業種
- コンサルティング業界 その他
- 職種
- 経営企画、事業企画・事業開発
- 年収
- 600万円~1,000万円
- 勤務地
- 東京都
- 仕事内容:
- 温室効果ガス排出量、環境・社会情報などを第三者の立場として確認し、データの透明性/信頼性を高めることで、持続可能な社会の実現に貢献。審査員として第三者検証(JAB認定の検証機関)業務をお任せします。具...
-
- 求人番号:150852
海外展開あり
大手企業
土日祝休み
業界最大手の社団法人
GAP 認証 審査員
- 業種
- コンサルティング業界 その他
- 職種
- その他 コンサルタント
- 年収
- 600万円~1,200万円
- 勤務地
- 東京都
- 仕事内容:
- GAP認証を含めたISO規格等の第三者認証機関として審査・各プロセスの管理業務審査業務/検証業務【有資格者のみ】顧客管理、審査員・認証組織を含む情報管理・および審査の運営管理(日程調整等を含む)正職員...
-
- 求人番号:150850
海外展開あり
大手企業
土日祝休み
業界最大手の社団法人
審査・管理・開拓(ISO認証)
- 業種
- コンサルティング業界 その他
- 職種
- 経営企画、事業企画・事業開発
- 年収
- 600万円~1,000万円
- 勤務地
- 東京都
- 仕事内容:
- ISO規格等の第三者審査(JAB認定、ISMS-AC認定の審査機関)に関わる業務をご担当頂きます。・ISOのマネジメントシステム規格について、第三者審査サービスを提供するための管理業務・品質や環境、食...