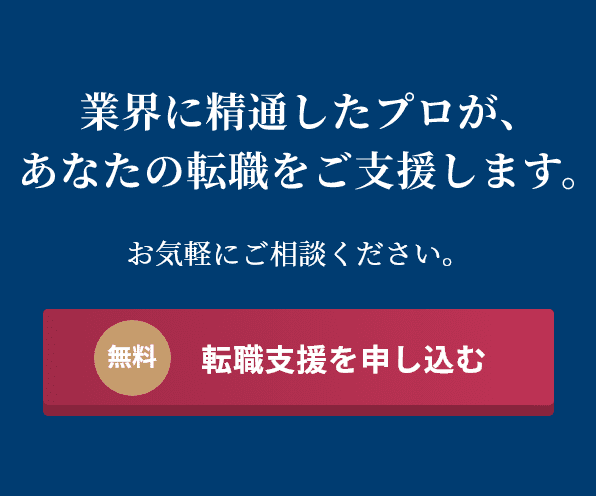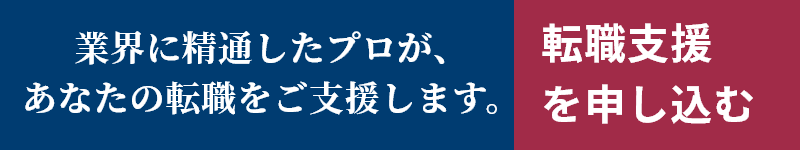業界情報
地域経済活性化支援機構(REVIC)で働く魅力と目指せるキャリア
目次
地域経済を支える事業者の支援を通じて、地域経済の活性化を担っているのが、地域経済活性化支援機構(REVIC)です。
今回はREVICでの勤務経験を持ち、現在はMBK Wellness株式会社 タレントパートナー事業本部長を務める大原に、REVICで働く魅力や目指せるキャリア、さらにどのような方に向いているのか、伺いました。
REVICとは
地域経済活性化支援機構、通称「REVIC」は、その名の通り、地域経済の活性化を目的に設立された機関です。
その原点は、2008年のリーマンショックに端を発する世界的な金融危機にあります。日本国内でも地域経済が大きく冷え込み、多くの中小企業が深刻な経営難に陥りました。こうした状況を受け、2009年に「株式会社企業再生支援機構(ETIC)」を設立し、過大な債務を抱える中小企業等の事業再生支援に取り組んできました。
しかしその後も、地域経済の低迷は続き、事業再生支援だけでなく地域経済の活性化に資する支援の推進が喫緊の政策課題になっていました。こうした背景を受け、2013年には株式会社企業再生支援機構法が改正され、支援対象や機構の役割が拡大されるとともに、組織名も現在の「地域経済活性化支援機構(REVIC)」へと変更されました。
さらに2014年には、再チャレンジ支援業務やファンド出資業務なども追加され、支援の幅は大きく広がっています。その後も、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済への影響など社会情勢の変化にも柔軟に対応しながら、業務期限の延長や制度の見直しを重ね、事業者に必要な支援を行っています。
地域の産業や経済の活性化には、各地域の事業者の成長支援や新陳代謝の促進が欠かせません。REVICは事業者を支える地域の金融機関と連携しながら、各事業者に応じた支援を行い、地域経済の活性化に貢献しています。
REVICの事業内容
REVICでは、新興企業・成長企業・成熟企業・衰退企業といった、あらゆるライフステージにある事業者からの相談を受け付けています。
REVICには、経営執行の経験者をはじめ、経営・財務コンサルタント、弁護士、公認会計士、M&Aアドバイザリー、投資業務経験者など、多様な分野の専門家が在籍しており、各事業者の状況を適切に評価・分析したうえで支援を行っています。
具体的には、活性化ファンド業務、ファンド出資業務といった成長支援、事業再生支援業務、事業再生ファンド業務といった再生支援、再チャレンジ支援、人材支援など事業者ごとの課題やニーズに応じて多彩な支援を行っています。
入社までの歩み
―これまでの経歴を教えてください。
新卒で野村総合研究所に入社し、コンサルティング部門で経営コンサルタントとしてキャリアをスタートさせました。
最初は業務効率化や事業戦略等、一般的なプロジェクトに参加していましたが、途中より大手証券の自己資金投資ビジネスの投資先であった民事再生法を適用された中小企業のバリューアッププロジェクトに参加、当時の野村総合研究所コンサルティング部門では珍しく実際に企業に月曜~金曜まで常駐してバリューアップ活動を実施するような働き方をし、中小企業の経営実態を目の当たりにしました。
その後、大和証券の自己資金投資部門であった大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツに投資担当として転職、在籍した5年のうち大半は三洋電機案件に案件担当者として関与、具体的には三洋電機への投資検討・実行、投資後は同社大阪本社の経営企画本部に常駐・バリューアップ、最終的にパナソニックグループヘのエグジットまでを担当しました。
こうして、投資検討・実施から、バリューアップ、エグジットまで一通り経験した状態で、2010年に企業再生支援機構(現:地域経済活性化支援機構(REVIC))に入社しました。
―なぜ、企業再生支援機構(現:地域経済活性化支援機構(REVIC))へ転職しようと思われたのですか?
以前在籍していた大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツでは、大和証券グループの資金を使った自己資金投資を行っていました。2000年代初頭から投資事業に取り組むPEファンドや証券会社が増え、当初投資した企業は結果的に利益を確保できるケースが多かったのですが、2008年のリーマンショックを機に企業経営の難しさが浮き彫りになり、証券会社が自己資金で投資を続けることに対して疑問の声が高まり、次第に投資を控える動きが強まっていきました。
そうした状況のなか、個人的に野村総合研究所において民事再生法適用企業の再生支援経験があり、この分野に対する強い思い入れがあったのに加え、社会の流れや、自身の関心・キャリアなどが重なり、企業再生支援機構の企業再生チームへの入社を決めました。
今回は私自身が企業再生チームで働いていたため、特に企業再生業務に関する話しをさせていただきます。
REVICとPEファンドとの違い
―REVICの業務は一般的なPEファンドの業務と比べて、どのような違いがあるのですか?
直近において、PEファンド各社が企業再生投資をするケースは非常に少なくなっており、ほとんどが事業成長投資もしくは事業承継投資となっているので、事業再生に関与できること自体が大きな違いとなります。
とはいえ、REVICが手がける再生支援において、支援決定(=PEファンドにおける投資決定)に向けたデューディリジェンス・バリュエーション・契約書締結等業務内容は通常のPEファンドにおける「投資検討業務」と大きく変わりません。
ただし、再生支援であるが故に通常の投資業務と大きく異なる点もあります。
1つ目は、支援決定後の事業計画を詳細に作り込んで支援決定する点です。具体的には、どの事業を撤退・存続させるのか、どの拠点を閉鎖・存続させるのか、人員削減含めたコスト削減はどの程度実行するのか等です。
2つ目は、金融機関との債権放棄・リスケ交渉が発生する点です。
REVICは支援決定先企業に融資をしている金融機関からの相談を受けるケースが多く、支援決定の段階で債権放棄・リスケなどに関する金融機関との調整をすべて済ませたうえで支援決定を行います。
また、支援決定後のプロセスにおいて大きく異なるのは、担当者が長期間に渡り企業に常駐し、常勤取締役等の役割を果たしつつ、実際の経営現場に深く入り込みながら再生を進めていく点にあります。
PEファンドは人員が限られていることもあり、投資担当者が企業に長期間常駐してバリューアップを行うことはほとんどありません。一部のファンドでは専任のバリューアップチームを組んで常駐することもありますが、常勤取締役ポジションを受けて常駐し、日々の業務に深く関わりながら再生に取り組むケースは非常に稀です。
一方、REVICの企業再生チームに入社する方は、支援決定先企業に常駐して再生プロセスに深く関わることになります。そのため、例えば30歳代で常勤取締役として働く経験ができますし、事業会社におけるCxOや経営企画、CFOのようなポジションを志向する人にとっては、非常に良い経験・キャリアを構築できると思います。また、支援決定に向けて様々な検討を行うため、投資業務の経験がない方も実践を通じて投資スキルを身に着けることが出来る点も非常に魅力です。
投資業務がメインのPEファンドに比べ、REVICでは投資後の企業再生業務を中心により幅広いスキルを身につけることができます。
―在籍時はどのような業務を担当されていたのですか?
私が過去に関与したプロジェクトの中で印象的な業務だったのは、早期退職制度を活用した人員削減があります。人員削減の対象となる方々と直接お話しをすることもあれば、時には組合の皆さんと徹夜で議論・交渉を重ねることもありました。
当時は大変でしたが、今思えば、貴重な幅広い経験を積むことができたと感じていますし、その後、別の会社でも早期退職制度等による人員削減を実施する機会があり、REVICでの経験が大いに活きました。
もちろん、人員削減は行わないに越したことはありません。
しかし、会社を存続させるためにはどうしても避けられないケースもあります。そうした場面では、実際に自分が経験しており、場合によっては自ら対応できた方がその施策の実行力に圧倒的に差が出ます。
また、再生支援を重ねる中で、企業再生を実現するために取り組むべき施策は共通項があることも感じました。
まず、財務面の立て直し、不採算事業の撤退・拠点の閉鎖、人員削減を含めたコスト削減を行い、事業を再生させる時間を確保します。それと同時並行で注力するべきビジネスの成長政策を矢継ぎ早に企画・実行し、業績の回復・成長を図ります。また、それと同時に人事制度変更やマネジメントチーム構築します。
つまり、企業の存続させるための時間を確保している間に、伸ばすべき事業を伸ばす、そのための会社の基盤を構築するということです。こうした経験や考え方は、企業再生を必要としない企業に転職しても役立つと感じています。
多彩な専門家が集結し、チームで企業を支援
―REVICでは、どのような方が活躍されているのですか?
前述したように、弁護士、会計士、経営・財務コンサルタント、M&Aアドバイザリー、投資業務経験者等、多彩な分野の専門家が集まっており、それぞれの専門家がチームを組んで企業再生に取り組んでいるため、自らの専門性を活かしながら、異なる分野も学んでいける環境が整っています。
私の場合は、投資業務と経営コンサルティングの両方の経験があったため、入社時には「ビジネス寄りでいくか、それとも投資寄りか」と迷いましたが、最終的にはより興味が強かったビジネス系のポジションで入社し、在籍時はビジネス領域を中心にカバーしてきました。
―担当する企業は、どのように決まるのでしょうか?
プロフェッショナルファーム同様、必要なプロジェクトが出て来る度に人がアサインされて、担当者の割り振りは、その時点で並行して進めている他プロジェクトの状況などを踏まえて決定されます。
私は在籍していた約3年半のうち、およそ2年半〜3年にわたり、上場していた製造業グループの企業再生支援に関わっていました。
その会社はM&Aによって成長してきた会社で、国内外に多くの子会社を抱えていましたが、リーマンショックの影響を受け、多くの子会社が経営難に陥り、国内外問わずグループ全体で再生が必要な状況にありました。企業の売上規模はそれほど大きくはないものの子会社の数が多く、非常に難しい案件でした。
本プロジェクトは、私を含め15人以上で企業再生プロセスを進めており、実際に私は企業再生の優先度が高かった子会社に常勤取締役として赴任していました。通常のPEファンドにおいて投資先に多くの人を張れないため、REVICらしい案件だったと感じています。
REVICで働くメリット
―REVICで働くメリットは、どのような点にあると思われますか?
メリットは大きく2つあると思います。
1つ目は、「若いうちから社長や取締役といったポジションを任され、投資業務や再生業務を通じて実践的なスキルを身につけられること」です。
一般的に企業の取締役になるのは簡単ではないですが、REVICでは30代でそのポジションを任されるケースも珍しくありません。実際、私も35歳で当時の企業再生支援機構に入社し、30代後半で初めて取締役として現場に常駐する経験をさせていただきました。若いうちから経営に深く関わるポジションを任され仕事に取り組んだ経験は、今後のキャリア形成において大きな財産になると思います。
2つ目は、「その後のキャリアにおいて、REVICで一緒に働いた仲間たちと、さまざまな形で再び協業できること」です。
当時、企業再生支援機構は5年間の時限的な組織として設立されたため、当時一緒に働いていた方の殆どは現在他の企業において活躍します。REVICはその後、複数回期間延長をしており、時限的組織としての位置づけは私が在籍していた当時と多少異なるものの、その流れは現在のREVICにおいても大きく変わらず、多くの方が一定期間在籍した後、次のキャリアへと進んでいると聞いています。結果的に、実力をよく知る元同僚がさまざまな業界で活躍しており、新たなフィールドで仕事をともにする機会が数多くあります。
例えば、私が在籍していた頃のメンバーの中には、PEファンドへ転職した方、PEファンド投資先企業で社長・取締役を務めている方、通常の事業会社のマネジメントとなっている方、アドバイザリー系のコンサルティングファームに戻った方などがいます。私自身も当時一緒に働いていた弁護士・PEファンドに在籍する方々と仕事をともにする機会が多々あります。また、元同僚が働いているPEファンドの投資先社長を元同僚が務めているケースもあるくらいです。
独立される方も多く、特に会計士の方々は独立するケースが非常に多くなっています。その方々と特定のタスクに絞って一緒にプロジェクトを進めることもよくあります。
日本において転職は盛んになってきていますが、REVICのように一緒に働いていた仲間がこれほど多様な業界に転職するのは非常に珍しく、実力を深く知る仲間同士が互いの専門性を活かしながら再び協業できる機会が多い点は、他の企業にはない大きな魅力だと感じています。
REVICは“キャリアの通過点”広がる多彩な選択肢
―転職をされる方も多いとのお話でしたが、REVICを経て皆さんどのようなキャリアを歩まれるのでしょうか。
当時はコンサルティングファーム出身者が非常に多く、他には証券会社や金融機関でM&Aアドバイザリー業務に従事していた方、会計士、弁護士など、いわゆるプロフェッショナルファーム出身者が多くいました。転職先としてはPEファンド投資担当・PEファンド投資先CxO、事業会社マネジメントとして転職するケースが非常に多く、プロフェッショナルファームではなかなか経験できない“現場感”をREVICで経験し、キャリアチェンジした方が多かったと記憶しています。
私自身も事業会社の取締役として転職し、その後はPEファンドや投資先企業2社の取締役を務め、現在に至っています。プロフェッショナルファームのキャリアを歩んでいたなかで、REVICにおける経験を経て事業会社系のキャリアへとシフトしました。REVICでの勤務経験は私にとっては大きな転機だったと感じています。
個人的な感覚として、REVICは一定期間働くことで様々なスキルを身につけ、次のキャリアへとチャレンジしていく場所だと感じています。長年在籍してここでキャリアを築いていくというよりは、キャリアの通過点という考えを持っている方の方が、REVICでの時間をより有意義なものにできるのではないでしょうか。
REVICが求める人材
―REVICには、どのような方が適任だと思われますか?
REVICは、その名の通り、地域の経済活性化を目的に、それに資する企業の再生や成長支援を行っています。支援対象となるのは、地域の中核を担う企業や競争力はあるものの経営がうまくいかずに衰退してしまっているような中堅・中小企業が中心です。
こうした企業の再建には、大企業を相手にする場合とは異なるアプローチが求められます。
まず重要となるのは、「当たり前のことを着実にやる」ことです。
そのうえで、現実的な企業戦略・事業戦略を描き、それを一歩ずつ実行に移していく必要があります。自ら営業活動をして必要に応じて人員削減も行う、新たな施策を実行するために従業員の皆さんとコミュニケーションを重ねて変革を実現する、コスト削減のリストを一から作成してひとつひとつの項目の削減可能性を検討・実行していくような、地道な活動を積み重ねて成果を出す、こうした経験を積みたい方には、REVICは最適な環境です。
また、転職段階で再生支援経験は不要、コンサルティングファーム・FASキャリアの方はフィット感が強く、監査法人のみ勤務経験の公認会計士や事業会社キャリアの方も転職できる可能性があります。
年齢を問わず採用のチャンスはあるので、こうしたバックグラウンドを持つ方や、アドバイザーからプリンシパルにキャリアチェンジしたいとお考えの方は、ぜひチャレンジしてみてください。